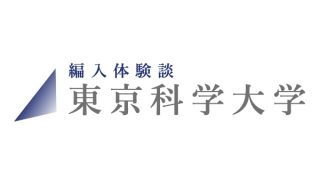自己紹介
名前:まさ
出身高専:九州内の高専 物質工学科
学科順位:3年次 2位、4年次 2位
受験年:2025年
受験大学(受験科目):九州大学 工学部 応用化学科
併願大学:専攻科
部活や資格:運動部
TwitterID:@o_MasaAyu11
なぜ編入をしようと思ったか
将来は環境問題に関する研究や製品開発を行う職に携わりたいという希望がありました。これを行うためにも大学への進学は必須であると考え、地元のなかで最も専門的により深く学ぶことができる九州大学を選択しました。
学年ごとの勉強内容
1~3年
1,2年生は授業で分からないことがないように勉強し、部活を行い、長期休みはバイト漬けでした。成績は大体3~9位/40人で特に1位を狙おうとか進学したいとは考えていなかったです。
3年生になり、先輩からの話や企業・大学の説明会などで高専からの大学編入の詳細について知りました。具体的に進路が決まっていた訳では無いですが、これからの進路選びに苦労しないよう成績はあげたいと思い1,2年以上に勉強を行いました。成績は2位でした。
4年前期
進路を決めるのに非常に悩むようになったインターンシップがありました。
私は大手企業の研究所で実験や研究を肌で感じ学びました。これがきっかけで研究職に就きたいという気持ちが強くなりました。
3年次の成績が2位で4年前期の成績も好調だったこともあり、先生から九大への編入をおすすめされ、両親も学費等気にせず進学して大丈夫だと言ってくれました。
しかしインターン後に企業と何回か面談もしていて、この辺りで本当に自分の進路が分からなくなりました。
4年後期
自分の進路に答えが出ないまま月日が過ぎていきました。大学にいける道を断ちたくなかったので定期テストの勉強をひたすらやりました。1位のクラスメイトが自分と天地ほどの差(1位と2位で平均が3点くらい違う)があり食らいつくように勉強しました。4年次の成績は2位でした。
進路についてはここで就職してこのままずっと働くのか?とか大学に編入してからもたくさんの道を選べるのではないのか?など色々な人の話を聞く中で考えるようになりました。
5年前期
4年次成績がクラス5%以内に入れたこともあり、ここでようやく大学進学の意思が固まります。
しかし、今まで定期テストの勉強がほとんどでTOEICの点数は絶望的でした(ここに書けないほどです)。4年春休みまででTOEICに区切りをつけ編入の勉強をしました。
九大編入の併願として自身の高専の専攻科を希望しました。本当は広島大学の一般を受けたかったのですが、試験日が被っていて受けれませんでした。
専攻科の試験は5年間の専門科目総復習の問題だったので、これまで習ったことを4,5,6月で振り返るように勉強しました。私の研究室も3/4が進学で常にピリピリしてみんな勉強してました。よく問題を出し合ったり、ここは重要かも!みたいな情報共有もしていました。
勉強しながらも研究や大学調べも十分に行いました。自分がやりたい研究や先生の名前・顔は頭に入れてましたね。自身の研究については色んな文献や先行研究を読み漁りました。
余談ですが、TOEICの点数が悲惨だったことや行きたい大学の研究室が英語で会話することがあるということもあり夏休みにオーストラリアに短期留学に行きました。英語でコミュニケーションをすることや生活を知るという面でとても経験になったので自分のやる気と両親の許可がある人は経験してみることをおすすめします。
試験当日
試験内容
九州大学工学部への編入は学校推薦でのみ受験することができます。口頭試問を含めた面接のみ行われました。一般受験の筆記試験はありません。
推薦条件はクラス順位上位5%以内です。
面接
試験当日
九大が車で通える距離だったので、当日両親に送迎してもらいました。集合時間も12時30分で時間に余裕を持って学校へ向かうことができました。前日入りに関してはわかりません。
集合時間になったら待機教室から移動し、応用化学科受験生の待機室へ移動しました。受験番号順に呼ばれ面接を受ける、終わった人から解散という流れです。
私は受験番号が後ろの方だったので他の受験者と待機室で少し話したりして緊張をほぐしました。面接が終わった後に連絡先も交換したりしましたね。
面接内容
時間:15分くらい、面接官5人、個人面接、受験者数6人、合格者数4人
→Q1 志望動機
→Q2 卒業研究の内容
→Q3 進路について
→Q4 自己PR
→Q5 英語って得意?
口頭試問1
→興味がある人名反応は?じゃあその反応をホワイトボードに書いて
→(マルコニコフ則と答えたので)アンチマルコニコフ則っていうのもあるよね、それに用いられる具体的な試薬とかってわかる?
※マルコニコフは人名反応じゃないツッコミはしないで、、汗
口頭試問2
→水のpHってどんな計算で表される?
→何も含まれていない水のpHは何?
→室内の水だとpHって7にはならないよね、酸性か塩基性どっちになる?じゃあその原因は?
→(CO2が溶けているからと答える)そのCO2をもっと溶かすならどうしたらいいと思う?
→他の気体が溶けたらpHってどうなると思う?
口頭試問3
→Sn1, Sn2反応について説明して
→生成物はどのようになる?
→Sn1とSn2の「1」と「2」ってどういう意味?
→一次反応と二次反応の違いって?
口頭試問4
→アミノ酸ってどのような物質をいう?
→タンパク質とアミノ酸の違いって?
例年面接ではQ1~Q4のことを深掘りされるのがほとんどで私も志望動機や卒業研究に関して詳しく練習しました。しかし受験者数が例年より多かったことからそれらは特に特につっこまれることなく早々と口頭試問に移りました。有機化学が専門分野の中で苦手だったので最初の質問は冷や汗ダラダラでした笑。
TOEICスコアを持っていかなければいけませんが、例年提示されていないようです。(今回も見せる必要はありませんでした。)しかし質問でもあるように英語能力は重要視されているのでスコアはある分に越したことはありません。私はTOEICスコアは包み隠さず話して、これからどうしていきたいか(留学に行く話をしました)を話しました。
後輩に伝えたいこと
私の進路の決め方はかなり特殊で遅い方だと思います。こんなダラダラならないように自分の意志をしっかりと持って考えて欲しいです!そうしたらもっと余裕を持って準備をすることができました。
インターン先の社員の方から言われた「就職か進学どっちの道を選んでも決して間違いではないよ。自分がやりたいことを正直に貫きなさい」(かなり美化)的な感じの言葉が私の自信につながっていました。さまざまな年齢職種分野の方の話を聞いて、どのような道があるのかたくさん知っておくことが大切がと思います。
進学したい大学への意志が強い人は大丈夫かと思いますが、志望動機や自身の研究に関して面接で話す内容に生成AIが考えた内容を入れるのは個人的にやめておいたほうがいいです。AIが考えたことが軸になってしまいがちですし、何より自分の言葉で自分自身を説明しないとどこかで必ず違和感が生まれます。しかし面接や口頭試問の練習相手としてチャット型のAIを使うのはアリです!私もお世話になりました!
先生を面接練習を行うと思いますがたくさんの人と行うのはあまりオススメしません。先生一人一人考え方が違います。ある先生はいいと言ってくれることがもう一方の先生は変えたほうが行ってきたり、、。正直混乱するので研究室の先生、担任の先生+αくらいがちょうどいいと思います。
前年度に同じ学科の先輩がここの応用化学科に進学されたので、面接や勉強、移動方法、当日には一緒に集合場所まで案内してくれたり、集合時間まで一緒に待っててくれたり、受験が終わった後は(口頭試問があまりできなかったことに対して)慰めてもらったり、アパート選びを教えてもらったりしました。とっっっっても強すぎる心の支えでした。
私も連絡いただけたら全身全霊手助けします。
オススメの参考書
私はほとんどが学校で買った教科書や資料で勉強しました。
アトキンス(物理化学)やマクマリー(有機化学)などの分厚い参考書は時間があればいいと思いますが、直前になぞるようにやるのは良くなかったです。
同じ進学組の友達とやっておいたほうがいい内容やいい参考書の情報共有をしましょう!