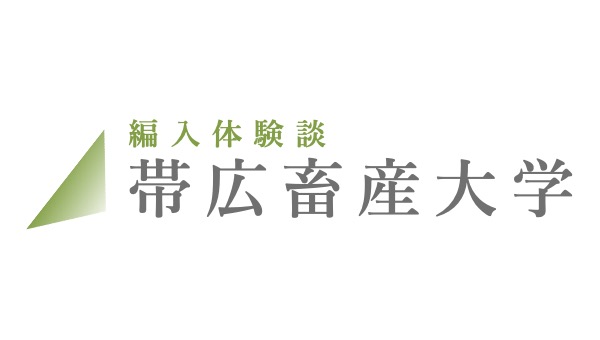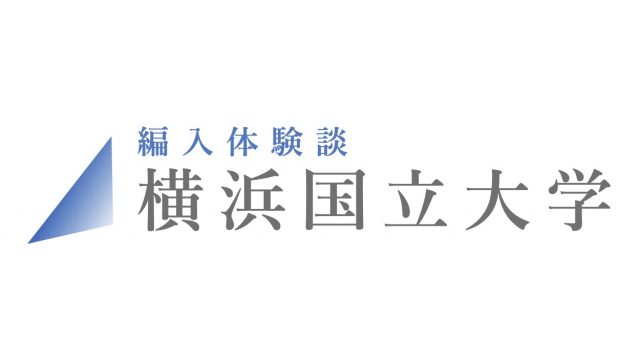自己紹介
名前:ks
出身高専:福井高専 電子情報工学科
学科順位:3年次:1位 4年次:1位
受験年:2025
受験大学(受験科目):大阪大学基礎工学部 ソフトウェア科学コース
併願大学:福井高専専攻科,豊橋技術科学大学 情報・知能工学系,筑波大学 情報学群情報科学類,大阪大学工学部 情報通信工学科目(出願のみ),東北大学工学部 電子情報物理工学科(出願のみ)
部活や資格:プログラミング研究会 基本情報技術者 TOEIC775
TwitterID:kssaaaaaaaaaaan
なぜ編入をしようと思ったか
高専で勉強していく中で、情報系の学問を理論からやりたいと思って志望しました。
科目ごとの勉強方法
数学
使用した参考書
〇編入数学徹底研究
〇編入数学過去問特訓
〇大学編入のための数学問題集
この3つは大学編入の際よく使われている参考書です。微分積分・線形代数の範囲のみ解きました。典型的な知識としては、大学編入のための数学問題集の方が網羅されていると感じます。一方、徹底研究・過去問特訓は、その中でも頻出の範囲の問題をより多く収録してあるイメージです。
〇ベクトル・行列・行列式徹底演習
難関大受験で使われているとされている、線形代数の参考書です。線形代数に関する知見が深まるため、上の参考書で詰まった、計算は出来るけど何をしているか分からないといった方に特に有効です。
〇細野真宏の確率が本当によくわかる本
阪大の離散確率はこれだけで十分すぎるほど戦えます。一方、まれにエントロピーなどが出てくることもありますが、確率よりは式変形の問題に近いように感じます。
その他、H23~の過去問を解きました。平成時代の問題はかなり手強く、実際その時の合格点も低いようです。
物理
使用した参考書
〇弱点克服 大学生の初等力学 改訂版
阪大基礎工の物理は剛体のみなので、ほとんどこの問題集で対応出来る…のですが今年に限ってはそうではありませんでした。1周目は単振動・万有引力の章を除く全て、2周目は剛体の部分のみ解きました。
〇電磁気学演習(黄色の本)
電磁気学の問題集だと恐らくこれがメインだと思います。しかし、編入で出ないような問題も数多く収録されており(それらの問題に限って難しい)、過去問を見ながら出そうな問題を中心に解くことを推奨します。一方、近年の電磁気の問題は、この本の例題・類題がほぼそのまま出るといったケースも多いので、やっておく価値は十分あります。
〇物理のエッセンス(熱力学分野のみ)
熱力学は高校分野の知識を使うことが多いので、この参考書が有効です。範囲としては、これらの部分を押さえておけば大丈夫でしょう。
・気体分子運動論(高校物理の教科書レベル)
・サイクルの各過程(等温・等圧など、マイヤーの関係式、仕事を積分で求める)
・熱力学第一法則(変化過程で何が変化して何が変化しないのかをしっかり理解しましょう)
その他、H23~の過去問を解きました。こちらは過去の年ほど難しいといったことはありませんが、何となく令和と平成で傾向が違うように感じます。
化学
特になし
英語
使用した参考書
・金のフレーズ
・文法特急
・ALL IN ONE TOEIC テスト 音速チャージ!
・abceed有料プラン
TOEICは700点以上は欲しいです。基礎工に関して言えば、800点以上あると安心して受験に望めると思います(700点台でも十分合格は見込めますが、他の方の体験記を見て不安になることがありました)。
一部のTOEIC一年前まで有効の大学が第一志望でもない限り、3年の終わり頃に取り終えてしまうことを強く推奨します。4年生から編入勉強ばかり出来る訳でもないので…
専門科目
基礎工学部は口頭試問のみです。筑波大学用にAtCoderをやって、後は基本情報の参考書の範囲をメインに対策しました。今年から傾向が変わっており、結果的にはあまり役には立ちませんでしたが…
試験当日
試験内容
数学
大問1 5~6.5割
例年2変数関数の微積や微分方程式、二重積分がメインでしたが、今年は1変数の積分に関する問題でした。(3)の積分が解けず、(4)は(3)の数値だけを使うことに気づいて(部分点狙いで)慌てて解きましたが、微分で係数をつけ忘れた気がします。
大問2
9~10割 基本的な固有値、固有ベクトルの問題から始まり、ケーリー・ハミルトンの定理を使った行列の多項式の計算、最後に対角化不可な行列のe^Aの計算が出題されました。最後の問題に関しては、A^2などを計算して実験するとA^nの形が予想できたので、数学的帰納法で示してからe^Aの計算を行いました。ケーリー・ハミルトンの定理を使った計算が自信がないので、9~10割としています。
大問3
10割 サイコロの6が1,2回出たら即終了の試行に関する問題でした。余事象を考えることで楽に解くことが出来ました。合格のためには必答だったと思われます。
物理
大問1(力学) 選択せず
例年剛体の力学がメインでしたが、今年はまさかの円運動に関する導出?問題でした。ベクトル解析の知識を使って計算するみたいな問題で、殆どの受験生が対応出来なかったと思われます。こういうこともあるので、物理で電磁気学or熱力学を捨てるのはやめた方がいいでしょう。
大問2(電磁気学) 10割
最初に無限/有限長の直線電流による磁場を求めて、次に正方形、正N角形で中心に出来る磁場を求めて、最後にNを無限にして円電流の場合を求める、といった問題でした。黄色い本の例題/類題レベルだったように感じますが、例年と違ってビオサバールの法則が書いてなかったため暗記or導出必須でした。
大問3(熱力学) 9.5~10割
例年通りのよくあるサイクルの問題でした。単原子分子理想気体と明記されており、内部エネルギーやCv,Cpの記載はなく、公式暗記テストっぽい側面もあったように思えます。例年ポアソンの法則が問題文に記載されていたのですが、問題文の記載なしで使って解いた問題があるため、9.5~10割としています。
面接
口頭試問
〇フィボナッチ数列について説明
・一般式を書く
・再帰で書くとどのように計算される?
・もっと高速に計算する方法はあるか?
〇2の補数表記でオーバーフローを起こす条件
・2の補数について説明
・2の補数はどの数までの範囲まで表現できる?
例年は大問1はアルゴリズムとデータ構造、大問2は計算機/セキュリティなどから選択という形式でしたが、今年は大きく異なっていました。
面接
・志望動機
・大学院に進学する予定はあるか?
・他に受験した学校は?
例年試験問題が目の前に置かれていて、試験の出来等を聞かれるらしいですが、私の時にはありませんでした。数理科学コースの方ではあったようです。
後輩に伝えたいこと
受験勉強について
他の方の体験記ではTOEIC800↑のものが多くありますが、700点台でも十分受かる可能性はあります。ただし、試験前にTOEICの差が気になるぐらいなら800↑を目指したほうがいいでしょう。私は凄く気になりました。
個人的な意見になりますが、毎日勉強をしようとすると課題の締め切りなどが重なった時に高確率で挫折します。早い段階から初めて、週3~5日稼働で週10~20時間勉強、といった感じの勉強計画を立てると挫折しにくいと思います。長期的な勉強計画としては、以下のような例が理想に感じます(他の大学を受ける方は、ここに英語や化学といった科目が入ってより時間が必要になることもあります)。
[3年前期・後期] TOEICを800以上取る。
[4年前期] 数学系の参考書を1~2周する。
[4年後期] 物理系の参考書を1~2周、数学系をもう1周する。過去問を解き始める
[5年前期] 過去問を解けるだけ解く。同時に、参考書で抜けている知識がないか確認する。
分からない/自信のない問題を生成AIに聞く際は、鵜呑みにしないように注意しましょう。考え方から間違っていることも割とあります。
受験前後・当日について
大阪大学は願書を自分で取り寄せる必要があります。忘れずに行いましょう。その他にも、卒業証明書等は学校で事前に作成してもらう必要があるので、早めに申請するようにしてください。
試験終了後、受験番号の書き忘れ等の確認なしに回収されます。終了前に必ず確認するようにしましょう。
その他
一般入試と異なり、編入試験は人によっては孤独な戦いを強いられることもあると思います。インターネット等で受験仲間・編入体験者と話したり、定期的に心身をリフレッシュすることでモチベーションを保ちましょう(逆に、周りの雰囲気に依存せず勉強できる方は、編入試験でかなりの強者に入ると思います)。
オススメの参考書
各科目で述べた参考書 特にベクトル・行列・行列式演習はオススメです。線形代数の問題にかなり自信がつきます。
私は受験勉強の時間が取れず何周も出来ませんでしたが、3周ぐらいするのが理想のように感じます。1周目だけだと、知識が抜けている部分も多くありました。