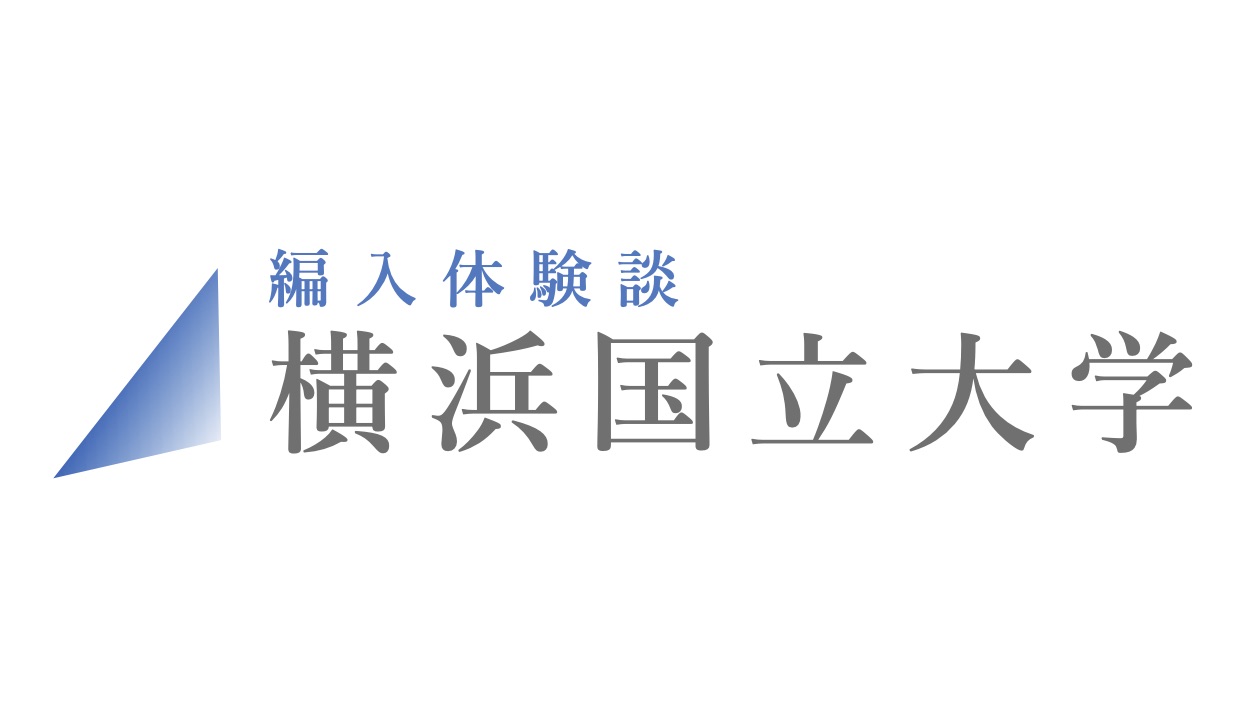自己紹介
名前:Satsuki
出身高専:高知高専ソーシャルデザイン工学科まちづくり・防災コース
学科順位:順位は聞いておらずわかりません。ずっと3~5位くらいだと思います。
受験年:2025年
受験大学(受験科目):横浜国立大学 都市科学部 建築学科(2年次編入)
受験科目:建築史 / 建築計画 / 建築環境工学 / 建築構造学・構造力学 / 建築生産 / 建築設計製図(ポートフォリオ持参) / 面接
併願大学:奈良女子大学工学部工学科
部活や資格:水泳部 1~4年生の時 四国高専大会1~3位 全国高専大会出場(リレー6位) / デザコン研究会(建築系の部活) 2年生から部長
なぜ編入をしようと思ったか
低学年のころから新しいことを知ることが好きで、自分の持つ視野を広げたいと思い大学編入したいと考えていました。
高専4年生の時に、1年生のころから憧れている横浜国立大学の建築学科に進学した先輩にお話を伺い、大学での学びなどについて教えていただきました。また、実務経験を持つ建築家による設計指導が受けられることや、私が特に関心を持っている都市計画の分野が充実していることが編入を決めた理由です。
学年ごとの勉強内容
1~3年
1年生
特に大きなことは何もせず、定期テストや日々の勉強を頑張る生活をしていました。
2年生
前期は1年生の時のように勉強を行っていましたが、勉強を頑張る意味が分からなくなり、後期の定期テストはありえない悪い点を取りました。
12月ごろから、3年次から分かれるコース選択のために興味のあるコースの先生にお話を聞きに行っていました。そこで建築系の先生に古民家再生ボランティアに誘われ、参加したことをきっかけに建築に興味を持ちました。そして流れるままにデザコン研究会という建築を学びたい学生が集まった部活に入りました。週に1回、建築雑誌を読み、建物についてディスカッションする読書会などに参加するようになりました。
また当時5年生の憧れの先輩が、横浜国立大学都市科学部建築学科に進学することを知りました。
3年生
現在所属する土木・建築系のコースに配属されました。心を入れ替えて勉強をまた頑張り始めました。それと同時に、8月にはじめて設計作品をつくり、高専デザコンに応募しました。(わからないことが多すぎて先生に頼りまくりました。)また、先生から勉強だけでは編入学試験に合格することは厳しいと聞き、学外活動に積極的に参加するようになりました。3年生の春休みに1か月間台湾に留学しました。また後期に出したコンペで賞を取ることができました。
4年前期
編入学試験の勉強をしなければ!と思いながら、難しくなっていく勉強と実験のレポート、設計課題に追われて毎日を過ごすことで必死でした。
当時、都市計画を学びたいと思い、東京大学工学部都市工学科を志望しており、夏休み前に配られたチラシに東京大学に編入学した大学生による都市計画分野のプログラム「実践教育プロジェクト」が行われると知り、応募し参加しました。
プログラムでPythonを用いた都市の分析手法や都市計画についての知識を学ぶとともに、大学生に編入学試験の話やその先の将来の話を聞き、編入学が自分の中でよりリアルになりました。
それと同時に、大学に編入学したら私もこのようなプログラムの運営に参加してみたいとも思いました。
また、それと同時に夏休みに設計事務所と広島大学にインターンシップに行きました。設計事務所では実務の建築設計にはじめて関わり、自分の勉強不足を実感しました。広島大学では都市計画研究室で、GISを使って分析を行ったりまちあるきを行いながら、大学生活とはどんな感じなのか知りました。
4年後期
本格的に編入学試験までの時間が無くなってきたことを感じ、とにかく焦っていました。しかし前期同様に学校の課題に追われ、その隙間時間に編入学試験の勉強を少しづつやっていました。また、後期に出したコンペで賞を取ることができました。
都市計画に興味はあるが、大学の学部で都市計画に絞らず、建築設計もちゃんとやりたい、できるようになりたい…と思うようになり、編入する大学を考え直しました。そのときに、横浜国立大学都市科学部建築学科に進学した憧れの先輩とオンラインで話し、横浜国立大学を第1志望にしました。(4年生の2月)
このときに先輩に過去問(H22~R4)と解答をいただきました。
春休みは併願校の選択肢を広げるために、数学のオンラインゼミに参加して編入範囲の数学の勉強を行いました。数学・英語の勉強を行いながら、横浜国立大学の対策として、過去問の1周目を行いました。
5年前期
編入学試験を受ける大学を、奈良女子大学と横浜国立大学に決めました。
卒業研究、設計課題、日々の授業などに追われながら、本当に時間がないと焦りながら編入学試験の勉強をしていました。自分のキャパに対してやることがあまりに多く、全然覚えられない自分に病みながら泣きながら勉強していました。寮で勉強できるタイプではないので、休みの日は近くのコメダ珈琲店に行き、朝から勉強するようにしていました。また平日は、暗記をずっとはできないので歩いて学校に行っているときや、休み時間、学校の課題の合間、寝る前などに行っていました。
人が周りにいないときは、声に出しながら読むとすごく覚えられました。また、文と図やイラストを併せて覚えるようにしていました。
スケジュール
3月~5月GWまで:横浜国立大学の過去問1周目
5月~6月中盤まで:横浜国立大学の過去問2周目/教科書を読む
直前:過去問をひたすら見て、頭で解いて暗記(5周くらい)/教科書も1日1教科読み3~5周して内容を暗記
またゴールデンウイーク明けに、横浜国立大学の都市計画研究室に研究室訪問に行きました。そこで憧れの先輩とごはんに行き、大学についてや面接について詳しくお話を聞いたり、みなとみらいに行き建築をみたり、いろいろ話しました。
4年生の夏休みに参加したプログラムで出会った大学生の方や設計事務所の方や研究室の先生に、ポートフォリオや面接を見ていただいていました、頼りまくりました。本当に感謝しています、ありがとうございました。
試験当日
試験内容
建築史(出来:9割)
建築計画(出来:10割)
建築環境工学(出来:5~6割)
建築構造学・構造力学(出来:9割)
建築生産(出来:9割)
建築設計製図(自作と証明できる作品を3~5作品 ポートフォリオ形式で)
私は4作品とこれまでの活動をまとめて、40ページのポートフォリオ持参
面接
面接はなごやかだったんじゃないかと思います。緊張しすぎてあまり雰囲気までは覚えていません。面接官は5人で片面ガラス張りの部屋でした。
都市工学科の建物で筆記試験を受けて、面接試験の前に建築学科の建物に移動しました。全員の控室が建築学科の建物の地下にある本に囲まれた部屋で、1個前になると1階の面接会場の横の部屋に移動しました。
面接時間:10分くらい
- 志望動機と将来の展望
- 併願校
- 奈良女子大学と横浜国立大学を選んだ理由(目の付け所がするどいといわれました)
- 2年次編入でもだいじょうぶか
- 学費の心配はないか
- 高知のまちの特徴
- 高知市中心部で都市計画から何ができると思うか
- なぜ建築に興味を持ったのか
- 横浜国立大学に来て気づいたこと
後輩に伝えたいこと
土木・建築融合学科なので、建築学科に比べると設計作品のレベルや学んでいるないように違いがあることがハンデとなりやすいです。実際に私はほかの受けた方に比べて設計作品のレベルがそこまで高くありませんでしたが、それを学外活動で補いました。積極的にいろんな活動に参加してみてほしいと思います。
高専卒の大学生や研究室の先生、先輩などたくさんの方に頼って、合格することができました。頼れる方を適度に頼って、勉強してみてほしいです。
たとえ無理と言われたとしても、編入学に関して保護者と意見が対立してしまったとしても自分が学びたいと思う学校を受けてほしいです。勉強を頑張って、結果がどうであれ成長できると思います。体調やメンタルを大事にしながら、頑張ってほしいです。
オススメの参考書
建築史:図説 建築の歴史(学芸出版社)
建築計画:1級建築士学科新体系テキスト 計画(TAC)
建築環境工学:図説 やさしい建築環境(学芸出版社)
建築構造学・構造力学:過去問,建築材料 第2版(森北出版株式会社)
建築生産:図説 やさしい建築一般構造(学芸出版社),建築構法(市ヶ谷出版)
横浜国立大学建築学科のシラバスを調べて使われている教科書を使うのもよいと思います。建築構法(市ヶ谷出版)にある図がでるので、買って勉強することをおすすめします。ほかの科目は学校で用いられているもので大丈夫だと思います。
そのほかは計算系の問題で演習量が不足すると感じたため、Chat-gptに問題作成をしてもらい、解いたりもしていました。