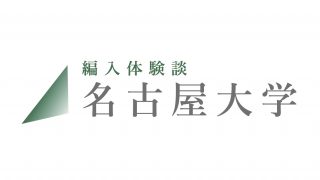自己紹介
名前:冷やさないワークデスク
出身高専:明石高専都市システム工学科
学科順位:1年次 B、2年次 B、3年次 B、4年次B (4年間の評価点平均は88くらい)※明石高専の成績は上位20%毎にABCDEの5段階評価を適用。
受験年:2026年度
受験大学(受験科目):大阪大学 工学部 環境・エネルギー工学科 環境工学科目
併願大学:香川大学 創造工学部 創造工学科 建築・都市環境コース(合格)、神戸大学 海洋政策科学部 海洋政策科学科 海洋ガバナンス領域(合格)、神戸大学 工学部 市民工学科(合格)
部活や資格:部活:クライミング部 資格:TOEIC 840(L430/R410)
Instagram:ryouyaaaa1218
なぜ編入をしようと思ったか
高専で専攻している土木工学に関心を持てなくなり、その一方で4年次にインターンで不動産会社に行き、デベロッパーという分野に興味を抱くようになりました。そこで、都市を経済や統計手法を用いて解析する研究をしたいと思うようになりました。阪大環エネでは、関心のない土木工学を試験科目として使わないこと、試験科目が少ないことや面白そうな研究室があったので第一志望にしました。また、将来のためにはより高い学歴が必要だと考え、編入を志しました。
科目ごとの勉強方法
数学
4年夏休みから数学に取り掛かりました。
夏休み
初めは、徹底研究と大学編入のための数学問題集をしていました。勉強のペースとしては、徹底研究を1日1章することを厳守していました。空いた時間で大学編入のための数学問題集に手をつけていました。初めは、必ず挫折すると思いますが周回することで解けるようになってくるので粘り強く頑張ってください!
※数学のスタートは徹底研究のみで十分です。
4年次 10月〜冬休み
徹底研究がある程度解けるようになったので過去問特訓に11月から手をつけました。A・B問題はそれなりに解けましたがC問題には苦戦しました。躓いた時は教科書や徹底研究などの1つ前のステップに戻り基礎を磨くことを心がけました。この時期は、徹底研究・過去問特訓・大学編入のための数学問題集しかしていなかったと思います。
4年次 1〜2月
応用数学(複素関数・ベクトル解析・確率統計)の学習に注力しました。複素関数に関しては、複素関数攻略への一本道という参考書を用いて学習しました。理論の説明もわかりやすく、演習問題もほどよい難易度で楽しく取り組むことができました。確率統計は確率統計(第2版)と確率統計問題集(第2版)を用いて学習しました。独学での学習だったためきつかったです。ベクトル解析は、数理工学社の応用数学という緑の教科書で基礎を身につけ、応用数学問題集で演習を積みました。公式証明と線・面積分を中心に取り組みました。
春休み〜受験直前
この時期から過去問(数学)と応用数学(ラプラス変換・フーリエ解析)に取り組み始めました。過去問は最新年度から解き始めました。私は、大問 2→1→3→4の順で解いていました。
簡単な年だと8〜9割(160~180/200)、難化した年だと6〜7割(120~140/200)程度の完成度でした。過去問で解けなかった範囲を上記の参考書を用いて復習する、抜けていた穴を埋める作業を受験日まで繰り返していました。応用数学(ラプラス変換・フーリエ解析)は上記の緑本と徹底研究を用いて学習しました。以上が数学の勉強スケジュールです。
物理
併願校で使用
併願大学の体験記は神戸大学工学部のみ後ほど投稿します。
化学
特になし
英語
TOEIC (4年次7〜12月)
(単語)
金フレ→黒フレ
(文法)
出る1000→ TOEIC L&Rテスト 990点攻略
(模試)
公式問題集→ 公式TOEIC Listening & Reading 800+
(シャドーイング)
音速チャージ→公式問題集、BBC Learning English(番組 6Minute English)
上記の参考書を使ってTOEICの勉強に取り組みました。
スコアの推移
7月 500(L270/R230)
8月 550(L300/R250)
9月 665(L415/R250)
10月 720(L400/R320)
11月 780(L415/R365)
12月 840(L430/R410)
専門科目
環境工学に関する小論文
春休みから環境工学PELとAnkiというアプリを用いて学習していました。
詳細
Ankiでは、エネルギー(各種発電系統)分野やカーボンニュートラル、水素・アンモニア利用、電化などの出題されそうなキーワードに関して概要(短所や長所含む)・現状・課題・将来予測などをカードにしてまとめました。EICネットや環境省HP、各種HPなどを参考にしてカードを作成しました。このアプリを使うことで、まとめ作業の短期化やエビングハウスの忘却曲線に則って、適切とされるタイミングで振り返りを求めてくれるため復習の効率化を図ることができます。また、環境工学科目はまだ過去問が少なく傾向が読みづらいため、幅広く知識を詰め込む必要があります。多くの本やサイトを閲覧して要点をまとめ、知識をつける事を心がけていました。5月頃から過去問を解き始めました。研究室(環境系)の先生とChatGPTに添削していただきました。過去問は2周しました。年によっては、文字数指定がなく罫線のみの解答用紙を用いて解答を作らないといけないこともあるので、とにかく量を書くことを意識しました。
試験当日
試験内容
環境エネルギーの受験者は5人でした。環境は2人(私とクラスメイト)でエネルギーは3人でした。エネルギー受験者の中の一人に同じ高専(他学科)の人がいてびっくりしました。環境エネルギーは、毎年3人程度合格を取ってくれるので他学科と比較して倍率は低めだと思います。
数学
数学は大問4つで2時間です。
大問1 線形代数
原点と2点によって作られる三角形の面積の計算・証明。また、一次変換によって何倍になるかという問題でした。 10割
大問2 微分方程式
連立微分方程式と同次形の問題でした。 10割
大問3 複素解析
写像、領域の変換の問題でした。 4〜5割
大問4 確率統計
正規分布の再生性と同時確率密度関数に関する問題でした。2〜4割
総括して、6.5割〜7割くらいの手応えです。
専門科目
専門科目は二問構成で90分です。
問題に関しては、過去問を取り寄せて確認してみてください。
文字数指定で頻出テーマだったので例年より書きやすかったです。低く見積もって7割、採点が甘い場合は8〜9割程度はあるかな〜といった手応えです。
面接
受験番号順に面接が行われました。
(環境→エネルギー量子の順番)
面接官はエネルギーから2人と環境から2人でした。
内容は、①志望動機、②取り組みたい研究、③卒業後の進路についてまとめて聞かれました。その後に深掘りと逆質問がありました。
体感15分くらいの圧迫感のない面接でした。同じ学科目を受けたクラスメイトも和やかな空間での面接だったと言っていました。
後輩に伝えたいこと
開示の得点は、612.7(72%)
推測にはなりますが、数学6.5割、専門7〜8割くらいかなと思います。
環境エネルギー工学科は、600超えれば安心して受かると思うので高席次のキープと筆記で7〜8割取ることを目指して頑張ってください!
オススメの参考書
教科別受験までの流れに記載しているので参考にしてください。