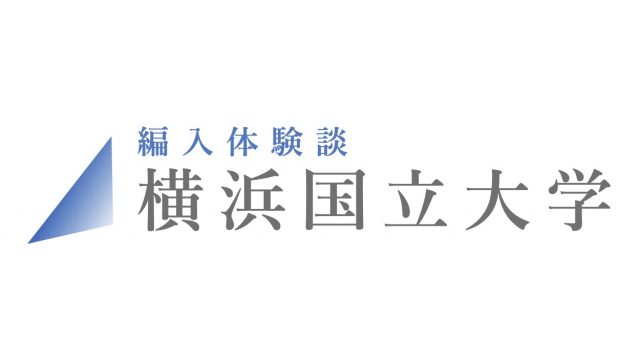自己紹介
名前:t
出身高専:K高専 電気系
学科順位:1年次:7位 2年次:9位 3年次:11位 4年次:9位
受験年:2026
受験大学(受験科目):広島大学 工学部 第二類
併願大学:愛媛大学 工学部 電気電子工学コース
部活や資格:バレーボール TOEIC820点
なぜ編入をしようと思ったか
4年12月時点で特にやりたいことがなかった。それなら進学しようと思ったから。
学年ごとの勉強内容
1~3年
定期テストのみ
4年前期
定期テストのみ。6月にTOEIC IPテストを受験して450点程度。
4年後期
12月の後期中間試験ごろに編入を決めました。この時点でまだ進学先は決めていませんでしたが、TOEICの提出が必要な大学が多かったのでTOEICの勉強を始めました。1月に受けたTOEICで660点。3月頭に受けたもので820点を取得しました。
5年前期
4月から本格的に編入試験対策を始めました。数学、電磁気、電気回路、力学を始めました。5月に愛媛大学工学部の入試があり、合格をいただきました。
試験当日
試験内容
試験内容は「一般」(志望理由スピーチ)、「専門」(電磁気、電気回路)です。
流れとしては、スピーチ内容、電磁気、電気回路の問題内容が書かれた冊子が配られます。
40分でそれらを解き、別室に移動した後に面接官の前でスピーチ→問題の解説という順番です。
まず黒板に回答をすべて書いて、最初の問いから解説していきました。制限時間はおそらく12分(電磁気6分、電気回路6分)
電磁気は円形コイルの問題でした。ビオサバール、アンペアの法則の理解が問われる問題。
電気回路はRLC回路の問題でした。どういう負荷を繋げば電力が最大になるか、この回路が振動する条件など、基本的な問題です。
問題が解けていなければ、ヒントをくれる場合もあるそうです。
解けていれば、その問題について深堀されます。
自分は電磁気の最後の問題について聞かれました。
「円形コイル二つに電流が流れている場合、時間的にどのように変化するか?」
「一方の円形コイルに流れる電流が逆向きになった場合どうなるか?」
のようなことを聞かれた覚えがあります。緊張していたので詳しくは覚えていません。
電気回路は時間が足りず、最後の問題まで解けなかったのですが、その旨を伝えると
「ではこの場で解けますか?」と言われました。
幸い簡単な問題だったのでその場で解ききったところで時間が来ました。
面接
ニュアンスが異なるだけで、毎年似たようなことが聞かれているようです。
「なぜ広島大学を選んだのか、大学で学んだことを将来どのように活かすか?」
が大筋です。聞かれることが多少変化しても対応できるように練習しておくとよいと思います。
後輩に伝えたいこと
・TOEICの勉強を早めにすること。
・進学先の大学を早めに決めること。
・大学を決めたら募集要項をきちんと確認すること。
高専の学生は英語の勉強が苦手な人が多いのではないかと思います。自分も820点を取るまでの3か月間はとてもしんどかったです。自分が受験した愛媛大学、広島大学は600点程度あれば大丈夫かもしれませんが、高いに越したことはないと思うので、早めに安心できる点数をとっておきましょう。TOEICの勉強法を「おすすめの参考書」欄に軽く書いておくので参考にして下さい。
進学先の大学は早いうちに決めておきましょう。自分は、進学を志したころは、レベル的に何となく神戸大学くらいかなと思い、力学の勉強をしていました。しかしよくよく調べると、自分にとって魅力的な研究室がなかったり、試験実施日が遅かったりと、自分に合わないなと思ったので受験をやめました。
自分のやりたいことが出来る研究室を選ぶのが一番です。
それがなければ、試験科目数、試験内容、試験実施日、その大学周辺の住みやすさなど、いろいろなことを加味して決めましょう。自分はそれで受験大学を決めました。
大学の知名度や偏差値だけで決めていると、無駄な時間を過ごすことになるかもしれません。
オススメの参考書
数学:徹底研究
力学:大学生の初等力学
電磁気:電磁気学演習(サイエンス社)、詳解電磁気学演習(共立出版)
電気回路:詳解電気回路 上下(共立出版)
TOEIC:金のフレーズ、公式問題集、出る1000、極めろリスニング
800点レベルなら単語は金フレのみで大丈夫です。必ず毎日夜に100単語、完璧でなくてもよいので覚えます。翌朝にその100単語を復習します。この際必ず音声付きでやりましょう。
出る1000の品詞問題、発展は難しければ飛ばして問題ないと思います。そのほかは何周もしましょう。
極めろリスニングは、パート3,4のみを繰り返しときました。最初は難しいですが、何度も聞けば聞こえてくるようになります。短期間で点数を伸ばすならリスニングをしましょう。
土日などまとまった時間が取れるときは公式問題集で模試を解きます。リスニング、リーディング通しで解くのが理想ですが、最初はLとRに分けて解いてもよいです。この模試も何度も解きましょう。
公式問題集を一通り解いたら、究極の模試、800+などを解いてもよいと思います。