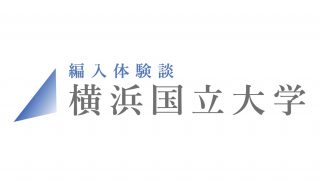自己紹介
名前:遙
出身高専:有明高専 創造工学科 建築コース
学科順位:3年次:1位 4年次:3位
受験年:2025年
受験大学(受験科目):筑波大学理工学群社会工学類都市計画主専攻 受験科目:TOEIC、数学、面接
併願大学:有明高専 専攻科
部活や資格:陸上部、TOEIC770点
Instagram:hr_rns2
なぜ編入をしようと思ったか
周りの子の設計してるものとかを見て、私は建築向いてないなって思いました。それと建築の視点からだけじゃなくて、もっと幅広い視点から社会と建築の関わりを勉強したいと思ったのがきっかけです。そのためには、”建築”というものの集合である”都市”を見ることでその関わりについて知るべきなのではないかと思い、社会と都市、どちらも学べる筑波大学の社会工学類都市計画主専攻にしました。
科目ごとの勉強方法
数学
勉強始めたての頃(4年生の2月頃、遅いのでもっと早めから始めた方が良い)は編入数学入門を最初から初めてわからない問題がほとんどでした。先生に質問しに行った時にこっちを先にするんじゃなくて、何年分かの過去問からその大学の出題傾向を把握してそれを重点的に勉強した方がいいと言われた。先生に手伝ってもらい傾向を大体把握した後は、マセマの教科書を使って体系的に勉強を進めていました。
社会工学類は線形代数、確率統計、微分積分が範囲で、線形代数、確率統計については全く分からなかったので基礎から叩き込みました。微分積分は高専での勉強の中でよく使っていたので特に重点的には勉強していないです。
春休みで線形代数、確率統計をマセマを使って勉強して、一回だけ学校に行って先生に授業のような感じで過去問の線形代数を教えてもらいました。ここで理解がぐんと深まりました。
マセマを使って基礎を大体固めた後は編入数学過去問特訓を使って実践的な問題に手を付け始めました。最初の頃はA問題でもわからない問題がたくさんありましたが、解いていくうちに考え方を理解できるようになり他の問題にも応用できるようになりました。”解き方”ももちろん重要ではあるが、なぜそのような解き方で答えが導けるのかという”考え方”を理解する方が良いと思います。
春休みが終わってからは、空きコマや内職をしながら数学を進めました。土曜日は午前中から休みを挟みながら寝る前まで数学をしました。日曜日は午前中のみ数学をして、午後は卒業設計の課題をしていました。しかし、休むのは大事なので日曜の午前中だけ頑張って午後は休む、という方が良いかもしれないです。(私自身前者のスケジュールで精神的にしんどかったので絶対休んだがいい!!!)
過去問は、春休み中からマセマでやった範囲で解ける問題を少しずつ解いてわからないところがあったら、ChatGPTやGoogle Geminiに聞いて、それでもだめだったら先生に聞いて教えてもらっていました。AIとの会話は自分の思考を深めながら、考え方を身につけることができるのでおすすめです(与えられた解答をそのまま飲み込むのではなく、自分で考えながらやる方が良い)。私は8年分をそれぞれ5回ずつ程解きました。正答率が中々伸びなくて苦しかったが、それでも前に解けなかった問題が解けるようになると嬉しかったです笑
毎週水曜日に数学の補講があっていたので、わからない問題をためて毎週通っていました。また、1人の先生に最初の1か月くらいは空きコマを使って授業をしてもらったり、放課後も遅くまで問題を教えてもらいました。本当にいい先生に恵まれてよかったです。
あとヨビノリさんの動画にはすごくお世話になりました。やっぱりテキストだけでは理解が難しいところとかをとても丁寧に、そして面白く解説してくださっているのでぜひ見てほしいです。
試験の2週間くらい前に、過去問を自分が得意な問題と苦手な問題で分けて、苦手な問題を3問やったら好きな問題を1問やる、みたいな感じで苦手をとにかく少なくしようとしていました。これが結構良くて、私の場合最後らへんはもう結構ぎりぎりの状態で勉強していたので好きな問題を解くことで勉強したくない!っていう意識をできるだけ薄めることができたと思っています。
物理
特になし
化学
特になし
英語
英語はとにかく基礎が大事だと思います。文法を中学校レベルからやり直して、「なんでこうなるの?」っていうところをできるだけ減らすように心がけました。
TOEICの勉強自体は、TOEICの公式問題集、金フレ、過去問ドットコム、天才英単語、この四つを使いました。
公式問題集で問題の出題傾向を把握し、金フレで単語を覚えました。
過去問ドットコムは、イディオムとか単語とか、語彙力アップのためにしました。このサイトは復習もできるし、解説もついてるし、正答率とかも見れるからおすすめです。
それとわからない単語は、天才英単語、というサイトを用いて調べました。このサイトは意味だけでなく、その単語の語源も見ることができるため、語源まで含めて覚えていました。例えば、escape(逃げる)という単語があったとすると、語源の部分で「ex, e(外に、外で)」と「cap, cep(取る、つかむ)」という感じで書かれているのでそこを覚えていました。そうすることで、実際の試験で分からない単語が出てきたときも大体意味を予測することができるのでおすすめです。
専門科目
面接
研究についての質問がたくさんされると思っていたので、ChatGPTやGoogle GeminiといったAIを用いて自分がやりたい研究は何なのか、考えを深めました。その中で、自分がやりたい研究テーマ、研究する意義(社会背景とか)、研究方法、期待される研究成果、学部、そして修士段階でどこまで研究するか、を考えました。AIを使って自分の考えを深めた後は、先生とその内容について話し合って細かいところや、壮大になりすぎた研究内容をスケールダウンさせていました。
自分やAIだけでは学部でどこまでできるのか、修士でどこまでできるのか。このあたりが検討をつけるのが難しかったので、先生からのアドバイスはすごく参考にしていました。
また、体験談から実際に出た質問をまとめてそれに対する回答を考えました。その回答から自分が面接官だったらどこに突っ込みたくなるか、を実際に回答を考えた紙に書きだしたりしていました。この過程を経たことで自分の考えがどうしてそうなったのか、というところまで考えることができたのですごくよかったです。
先生との面接練習は1か月くらい前から始めて週に2回くらい、色んな先生とやっていました。一つの回答に対して複数の視点から質問をもらえるので、色んな先生とやるのがいいと思います。
たまに友達にやってもらっていたのですが、学生という立場からもらえるアドバイスは先生とはまた違ったアドバイスになるので、おすすめです。また息抜きにもなりました笑
先生から、面接はちょっとフォーマルめな対話だよって言われて、「面接」という言葉に対して少し嫌悪感を軽減できました。あと私自身がすぐ緊張しちゃうのが良くないって思ってたんですけど、それも自分をよく見せたいって思ってるから大丈夫だよって。本番前の緊張は普通だからって言ってくれて気持ちがすごく楽になりました。
あと質問に対して回答を考えたのですが、その文章を丸暗記するのではなく、自分が何を伝えたいのか、その要点さえ押さえておけば後はスラスラ出てくるので要点を押さえるのが大事だと思います。
試験当日
試験内容
TOEIC(事前に提出)、数学、面接の3教科でした。
数学と面接が2日に分けて行われ、1日目が数学、2日目が面接でした。
数学は、
・線形代数(固有ベクトルから固有値を求める問題。対角化。ベクトルの一次性を示す問題。)→ 完答
・微分積分(連続可能性、極形式で解くやつ。マクローリンを使って円周率を近似する問題。これは(2)でbをどこに使えばいいか分からずその後の問題も解けなかった。)→ マクローリンの(2)からは解けなかった。それ以外は完答。
・確率(ポアソン分布のやつ。初見の問題で全く分からなかった。ポアソン分布は離散型なので離散型の期待値や分散の公式を使ったら解けたと思う。私は連続型だと勘違いしてしまった。)→ 0点
・統計(一般的なやつ。分散が分かってるときとわかってないときの期待値を区間推定する問題だった)→ 完答
ホテルに帰ってから自己採点したら7割くらい解けていたので自分的には安心できました。
面接
面接は、受験番号が1番だったのであまり緊張しなかったのが良かったかなと思います。面接官は3人いて、どの先生方も優しそうでした。圧迫面接はないと聞いていましたがもしそうだったらどうしようと思ってました。しかし、終始和やかな雰囲気での面接でした。3人それぞれ持ち時間があったのかな?、同じくらいの時間間隔で質問する先生が変わっていました。15分間が本当にあっという間でした。志望動機から深く質問されるので志望動機はしっかりと考えた方が良いと思います。
あと笑顔ってすごく大事だなって思いました。笑顔を意識するだけで、緊張が少し和らぐというか。いつもの自分が出せる気がしました。
質問内容としては、
・スウェーデンに行ったって言ったけどどんなことしたの?
→国際交流、英語でのコミュニケーション、異文化理解
・研究室に訪問したって言ってたけどそれはオープンキャンパスで?それとも個人で?
→個人で(ここで何か書き込みをしていたので研究室訪問は必ず言った方がいいと思った。さらに、それが学校が行っているイベントではなく自ら先生に直接連絡して行った訪問であるならなお良いと思う。)
・どの先生の研究室に行ったの?
→藤川先生
・じゃあ研究室は藤川先生の研究室に行くの?
→もともとサードプレイスの変遷について研究したかったが先生が私が修士に上がる段階でご退官されるので浦田先生のもとで研究したいと考えている。
・藤川先生と浦田先生って研究内容がだいぶ違うけど大丈夫なの?
→浦田先生の研究室の「レジリエント」という言葉が「弾力性」や「しなやかさ」といった意味を持っており、私がやりたい研究とマッチしていると感じた。
・「サードプレイス」ってあなた自身も普段利用してる?
→している
・都市の中のサードプレイスってどんなもの?
→多世代が交流できる空間や自習スペースといったもの
・「都市と学び」って関係ある?
→”都市”、”建築”、”社会”は関わっていて、その”社会”の部分をよりよくすることで”都市”自体が良くなると思う。またその逆ももちろんあり得る。この場合は社会=学び、であると考えているので関係している。
・修士に行きたいって言ってたけどどんな研究したい?
→学部では現状把握と課題抽出、修士では海外との比較や実装するためのアイデアを提案しようと考えている。
・今までの授業で一番印象に残っている授業は何?
→LL。スウェーデンの学生と交流し、自分の英語力のなさを知れたのが国際交流に関心を持ち始めたきっかけになった。
・スウェーデン以外で印象に残ってる経験はある?
→4年次のインターンシップ。町家の改修をされている設計事務所に行き、伝統を受け継いでいく設計スタイルがかっこいいと思った。
・伝統を受け継いでいくのと新しくしていくこと、これに対してあなたはどう思う?
→関心があまりない人に”町家”を知ってもらうという点では新しくしていくのも良いと思う。
後輩に伝えたいこと
体験談で受験番号は早い方が受かりやすい、というのをみて出願日の一番最初の日に届くように書類を提出しました。
また研究室訪問の際にできればその研究室の在学生の方と話をするのが良いです。先生のことや、学校での普段の生活、勉強のことなど学生目線での話を聞けたのが良かったです。また、図書館や授業で実際に使う部屋などを案内してもらい、どのような設備で学生さんが普段過ごしているかを見てみるのは自分が編入した後のことを想像しやすいのでおすすめです。
それと、勉強は早めに始めるに越したことはないので早めに始めたほうがいいです。アルバイトも春休み中は我慢して勉強に集中しましょう。
また、一緒に勉強を頑張ってくれる友達はすごく貴重なので一緒に高め合える人を探しておくのも大事だと思います。受験勉強は環境がほんとにすごく大事だと思います。
今回の受験で、友達や家族、先生、先輩、ほんとにいろんな人に支えられてるんだなっていうのを自覚できたすごくいい経験でした。これを機に周りに感謝することが増えたし、より一層周りの人を大事にしたいっていう気持ちが強まりました。
オススメの参考書
参考書:マセマ(線形代数、確率、統計)、編入数学過去問特訓
サイト:数学の広場 碓氷軽井沢IC数学教育研究所 歓迎
その他:過去問、ヨビノリさんの動画
参考書に関してはこの2つしかやっていないです。最初の方に編入数学入門を少しだけやりましたが、先生からのアドバイス以降はやっていません。
マセマでとにかく基礎を固めるのが大事です。基礎がなっていないと応用は解けません。細かいところまで説明がついているので、私はすごく助かりました。
過去問特訓は、色んな大学の問題が載っていて楽しかったです。全部で5~6周くらいしました(C問題は筑波大学以外の分はやっていない、また出題範囲でないところも飛ばした)
数学の広場。これは本当におすすめです。私も先輩から教えてもらったサイトなのですが、志望大学の過去問がたくさん載っていて解ききれないくらいでした。なので、直近20年分くらいのものから出そうだなって思う問題を選んで解いていました。
過去問は絶対解いたほうがいいです。試験勉強を始めようと思ったら参考書じゃなくて先に過去問を見たほうがいいです。それで傾向を把握しましょう。