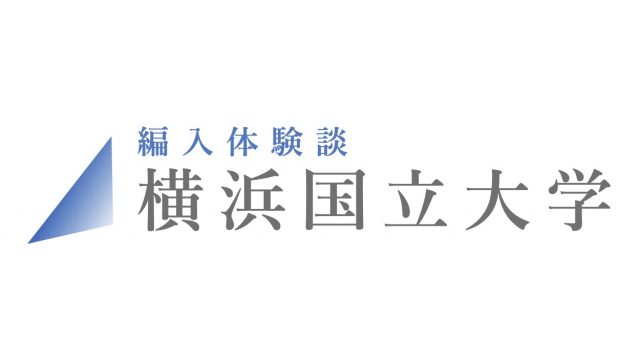自己紹介
名前:YS
出身高専:田舎高専 電気系の学科
学科順位:3年次:8位 4年次:2位
受験年:2025年
受験大学(受験科目):大阪大学 電子情報工学科 電気電子工学科目
併願大学:岡山大学(合格) 東北大学(不合格)
部活や資格:TOEIC 735点
なぜ編入をしようと思ったか
最初は就職と進学はどちらでも良いと思っていたが3年生になってから急に成績が上がったので編入について調べるようになると、なぜか就職という選択肢が頭から抜けていっていつの間にか編入のことしか考えておらず編入の動機はよく分からない。
大阪大学は、3年生から4年生になるときの春休みに数学の過去問を見て微積の問題が微分方程式だったので自分にとって解きやすいと感じたから第一志望にした。
学年ごとの勉強内容
1~3年
1年生から2年生の時は友達がおらず定期試験の過去問が手に入らなかったため成績は良くなかった。しかし、数学と物理だけは好きな科目だったため、毎回点数は高かった。化学は2年生の時に単位を落としたほど苦手な科目だったが、化学が得意になっておけば、編入試験の試験科目に科学がある大学も選択肢に入れることができるので、今1.2年生の人は数学、物理、化学だけはしっかり勉強しといた方がいいと思った。
部活などには入っておらず1.2年生の時はバイト学校が終わったらすぐに帰ってバイトをしといただけなので後に受ける東北大学の推薦入試で何もアピールすることがなく困った。
3年生になってからは友達が増えて過去問が手に入るようになり、専門教科が増えてきたことも合わさり、成績が上がった。3年生の7月に編入の勉強を始めるためにバイトを辞めたが結局4年生になるまで何も編入の勉強はしなかったのでとても暇だった。
4年前期
まず春休みにYouTubeで「編入過去問」と検索すると、「高橋ユウコ:高専数学と大学編入試験」というチャンネルでいろんな大学の過去問を解いておりそれを見ると筑波大学などの普通の微積の問題が出る大学の過去問は全然解けなかったが、大阪大学は最近の微積の問題は微分方程式しか出てなかったのでそこまでに習っていた範囲は難しかったが解けたので受けるなら阪大かなと思っていた。
春休み後は授業が始まると課題が増えて、その日に出た課題はその日のうちに終わらせたいタイプだったので、課題を終わらせるだけで疲れてしまい編入の勉強はしなかった。
5月にTOEICに申し込んでいたため単語帳一冊分急いで覚えて受けたが440点しか取れなかった。そこで、自分は一般受験は向いていないと思い、TOEICの勉強を辞めて、岡山大学の推薦入試で合格することを目標にして席次を上げることに集中した。実際は推薦の方が向いてなかった。
4年後期
前期の成績が3年生の時に比べてかなり良くなり、担任の先生に旧帝大どれか1つくらいは受けたらと言われて、やる気が出たため、志望校を大阪大学にきめた。夏休みの2ヶ月間TOEICの勉強をして10月に735点を取ることができた。TOEICの勉強ではabceedというアプリで問題を解きまくって勉強した。そこで終わっておけばよかったが12月にも2回受けてどちらも伸びなかったので意味がなかった。冬休みから数学の勉強を「編入数学徹底研究」を使って始めた。やはり、微積はできなかったが微分方程式以降の章はほとんど理解できた。なので、1月から学年末試験の1週間前まではずっと徹底研究の微積の部分を解いていた。
春休みになると、「編入数学過去問特訓」という問題集に取り組み、同時並行で徹底研究も周回していた。そして専門科目は物理と電磁気学で受けるつもりだったので大学生の電磁気学と大学生の初等力学、マセマの熱力学で勉強をした。
数学は春休みの半ばから過去問も解いていたが確率統計の勉強はしていなかったので、確率統計以外の部分を解いていた。
5年前期
5年前期は、東北大学の推薦入試を受けることにしたので、面接でいうことを考えたり、口頭試問の練習をしたりしていた。それと同時並行で電磁気学の過去問を解いて分からないところは、物理が得意な友達に教えてもらっていた。なので、6月が終わる頃に電磁気学は完璧になった。6月は岡山大学の一般入試があり、受かった。
物理の勉強は、なんとなく東北大学に受かる気がしていたので、4月と5月、6月はしていなかった。物理はまだ波動に関しては全くやっていなくて、やる気も出なかったので、物理での受験はやめて、電気電子回路で受けることにした。よって、7月からは電気電子回路の勉強と数学の確率統計の勉強を始めた。電気回路は得意なので少ししか勉強しなかったが、その分電子回路に時間をかけた。電子回路は図書館で「アナログ電子回路演習」という本を借りて問題を解き、過去問も解いていた。分からないところは学科の先生に聞いて理解を深めた。確率統計は学校の教科書を読んだり、図書館で「理解しやすい確率・統計」という本を借りて勉強していた。
夏休みになってからは過去問を毎日解いたり、今まで使った参考書を読んで忘れている知識がないか確認していた。
試験当日
試験内容
数学は例年通り、大問4つで線形代数、微分方程式、複素関数、確率統計の順で問題が出題された。時間は120分。線形代数は覚えていないが簡単だったと思う。微分方程式は連立微分方程式の問題が出た。複素関数は写像の問題が出た。確率統計は一目見た瞬間に解けないと分かったので(1)だけ解いてそれ以外は白紙で提出した。
数学の手応えは7割くらい。
電磁気学と電気電子回路はそれぞれ大問2問で合わせて90分の試験だった。電磁気の1問目は球と球殻の間に2種類の誘電体が挟まっているものに関してで、2問目はビオ・サバールの法則からアンペールの法則を導いたり、コイルにかかる力のする仕事を求めたりする問題だった。電気回路は過渡現象の問題で、電子回路はオペアンプの問題だった。専門科目の手応えは10割。
面接
面接では、
・志望動機
・卒研について
・併願校の合否
・志望する研究室の先生と事前にコンタクトはとったか
について聞かれてすぐに終わった。面接はあまり差がつかないと聞いていたので、前日に少し練習したが何も問題はなかった。
後輩に伝えたいこと
併願校は第一志望の勉強をしておけば受かるような大学にしておくといい。推薦入試で受かりたいなら面接で言えるネタを1年生の時から作ろうと努力した方がいい。試験当日は難しい問題があっても自分が解けないなら他の人も解けるわけがないと思うことで落ち着くことができる。過去問は編入の勉強を始める一番最初のタイミングで見るといい。
オススメの参考書
・編入数学徹底研究
・編入数学過去問特訓
・大学生の電磁気学
・アナログ電子回路演習
・理解しやすい確率・統計